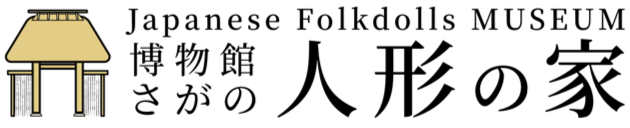小鍛冶
見立て小鍛冶
御所人形・見立て小鍛冶(みたてこかじ)

| 作品名 | 見立て小鍛冶 |
| 分類記号 | go222 |
| 年代 | 江戸時代末期 |
| 寸法 | H290. W310. D250. |
解 説
御所人形・見立て小鍛冶(みたてこかじ)とは、謡曲『小鍛冶』を題材に作られた「見立てもの」とされる作品の一。
▷『謡曲・小鍛冶』とは。一条天皇が『天下を治める宝刀を作るよう』夢のお告げを受ける事から始まる『宝刀・小狐丸』誕生秘話。
【あらすじ】
ある日、一条天皇は天下を治める宝刀を作るよう夢のお告げを受けます。
天皇は橘道成(たちばなのみちなり)を小鍛冶・宗近(むねちか)の元へ向かわせます。
しかし宗近は『良き相槌がいないと良き剣は打てない』と辞意を申しますが、道成は『勅命なれば辞することまかりならぬ』と命じます。
悩んだ宗近は氏神である稲荷明神へお祈りに出かけようとすると、童子に呼び止められます。
童子は帝から剣を打つよう仰せ付けられたことを知っていた。「壁に耳あり」というように直ぐ広まるものであり、まして帝の御用を賜ったのだから世間が知らないはずがないと言う。
そして、「大君の恵があるから剣を打てないはずがない」と勇気づける。
「漢の高祖・隋の煬帝・唐の鍾馗大臣などは剣の威徳により世を治めた。我が国では日本武尊が四方を敵に囲まれ、草に火をつけ攻められた時、剣を抜き四方の草を薙ぎ払い、火を吹き返し敵を滅ぼしたのだ。これから宗近が打つ剣もこれに劣らない程の物であろうから安心して帰りなさい」と言い、鍛冶の壇を作り待てば、必ず力を添えに来ると稲荷山の方へ消えて行った。
そこで壇を築き神に祈っていると、稲荷明神が童男の姿で現れ、壇に上がり相槌を仕る。剣の表には小鍛冶宗近、裏には小狐と銘を入れる。
「これこそ天下第一の名剣で、表裏二つの銘を打ったこの剣で天下を治めれば、国土も豊かになることであろう」打ち上がった刀を「小狐丸」と名付け、勅使に捧げ、雲に飛び乗って東山の稲荷の峰に帰って行くのであった。